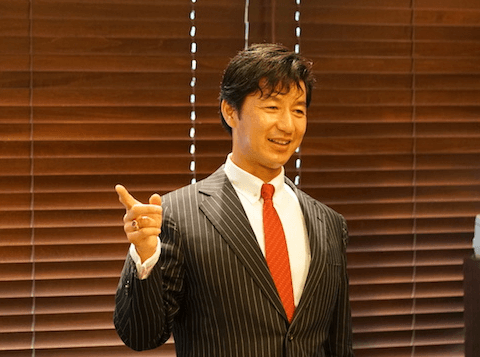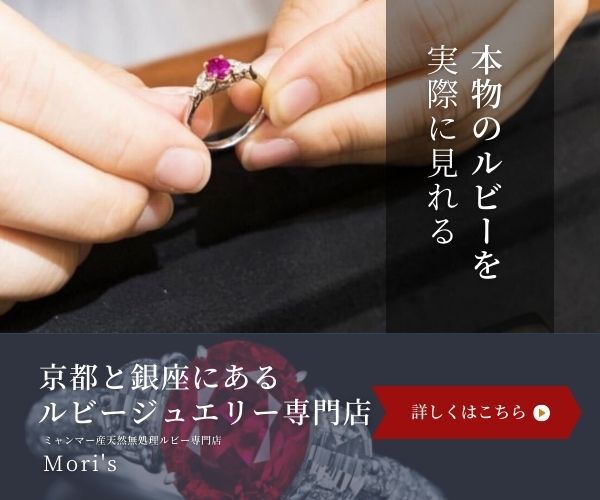宝石の物理的性質一覧なんて聞くと、難しい言葉に聞こえてしまうかもしれません。
実は、地球や宝石、また自然界の仕組みは勉強しにくい分野と言われています。
この記事では、宝石の物理的性質①【劈開 ・硬度 ・密度・ 磁性・展性・延性】について解説していきます。

そもそも、鉱物と宝石
鉱物は岩石を構成している素材のことです。現在5000種ほど見つかっていて、さらに新種が発見されています。
鉱物は大きく3つの要件が満たされていないと鉱物とは認められません。
- 地球がつくったものであること
- 決まった成分であること
- 個体であり結晶であること
鉱物の中でも美しさ、耐久性、希少性を兼ねそろえている物を宝石と呼んでいます。
鉱物の物理的性質 劈開など14個の特徴
鉱物の物理的性質は、物理的性質には鉱物種としての特徴が反映されるので、分析機器がないときに役に立ちます。
本来は鉱物の種を決めるために使われていましたが、鉱物種の定義が結晶構造と化学組成で決定されるようになってからは、補助的な役割にとどまるようになってきました。
鉱物の物理的性質は14個あります。
- 劈開
- 硬度
- 密度
- 磁性
- 属性、延性
- 色
- 条痕色
- 光沢
- 透明度
- 発光性
- 電気的性質
- 放射性鉱物とその利用
- 化学的性質
- 触感、臭い、味
この記事では1~5までを解説していきます。
①劈開
原子間の結合が特に小さいと、その方向と垂直な面で結晶が割れやすくなります。これを劈開と言い、割れた平らな面を劈開面といいます。
紙のように薄くはがれる雲母や、平行六面体に割れる方解石は、典型的な例です。
輝石グループと角閃石グループの劈開はいずれも2方向あり、互いになす角度が輝石類は約87°、角閃石は約124°です。
紙のように薄くはがれる、雲母の仲間「ケイ酸塩鉱物」
ここでは劈開を持つ鉱物として紹介した雲母という鉱物を解説します。
雲母の仲間はうすくはがれることで有名です。結晶をつくる原子の並び方は、サンドイッチのような層になっています。
- 白雲母:昔は、うすくはがしたものが窓ガラスに使われました。ウラル山脈産のものが、モスクワ経由でヨーロッパに輸出され、英語名の由来になっています。
- 黒雲母:鉄雲母や、色の濃い金雲母などをまとめて黒雲母と呼びます。花崗岩をつくる主な鉱物のひとつで、ペグマタイトのなかには大型の結晶ができます。
- 金雲母:金は含まれていませんが、金色に輝くことから名前がつきました。鉄を多く含むものは鉄雲母という別種になります。
- リチア雲母:リチウムをふくみ、ピンク色でうすい結晶は透明です。主に花崗岩ペグマタイト中に産出します。細かい結晶の集合体が多いですが大型の単結晶もあります。
- チンワルド雲母:名前は、チェコの産地ツィーノヴェツにちなみます。日本では、山梨県や岐阜県の花こう岩ペグマタイトの中に産出しました。リチウムと鉄を両方含む雲母をまとめた呼び名です。
- ソーダ雲母:外見からは白雲母との区別がむずかしいのですが、ひすい輝石や藍晶石など、圧力の高い場所でできる鉱物をともないやすいところが違います。
平行六面体に割れる、方解石
ここでは劈開を持つ鉱物として紹介した方解石という鉱物を解説します。
鍾乳洞の中のつららのような石は、方解石でできており、雨などの酸性の水に、溶けやすい性質があります。これは、炭素と酸素の結びつきが土台となる「炭酸塩鉱物」の特徴で、くじゃく石やあられ石もその仲間です。
方解石は、3方向に割れやすく、われ口は平面になります。透明な結晶は、物を二重に見せる性質があります。(複屈折)やわらかくナイフで傷がつきます。
石灰岩は、主に方解石でできていて、雨水に当たると少しずつとけます。石灰岩の成分をとかしこんだ水が集まり、洞窟の広い空間に出ると、ふたたび成分が結晶して、細かな方解石となり、それが集まって鍾乳石になります。
劈開を持つ鉱物は劈開面に沿って割れる
劈開のでき方は、結晶の構造を知ると分かりやすいです。結晶構造がわかると、その原子配列から劈開の有無、程度が予測できます。原子間の結合力に差が少ないところでの割れ口(断口)は、貝殻状だったり、不規則な形になります。
劈開を持つ鉱物なら、あるショックを与えるといつも劈開面に沿って割れます。
固体によって偶然、劈開面に似た平面で割れるものがありますが、これは裂開という現象で、原子間の結合によるものではなく、他の要因(集片双晶、不純物)
②硬度
鉱物の硬度はふつう、モース硬度で表されることが多いですが、硬度の表し方には次の2つがあります。
- モース硬度:鉱物同士を互いにひっかきあった時の硬度
- ビッカース硬度:ダイヤモンドの針を鉱物の結晶面や研磨面に一定の荷重をかけて押し付け、できたくぼみの大きさで硬さを表します。
よく混同されるのは「もろさ」です。もろさはハンマーなどでたたいたときの衝撃に対する抵抗の強弱です。硬くても、もろいものもありますし、その逆もあります。
③密度
密度の大きい鉱物は手に持ってみると、重く感じます。
一般に、金属光沢、金剛光沢を示すものが密度が大きく、脂肪光沢、樹脂光沢、ガラス光沢を示すものは密度が小さいです。
④磁性
一般的に、磁石を近づけると、磁石が吸いつけられるような強磁性を鉱物について、「磁性がある」といいます。磁性のある鉱物はきわめて少なく、Fe、Niを主成分とする元素鉱物、酸化物、硫化物に限られます。
⑤展性、延性など
固体に力を加えたとき、その力が小さければ弾性変形をします。力を大きくしていき、弾性限界を超えたとき破壊されずに変形し、加えた力を除いても元の形に戻らないことがあります。このような変形を塑性変形といいます。
- 弾性:力を加えると変形しますが、力を除くと元の形に戻る性質です。例 雲母
- 脆性:力を加えたとき、変形せずに破壊されてしまう性質です。例 方解石、ダイヤモンド、など
- 延性:力を加えたときに、破壊されずに細長く伸びて、元に戻らない性質です。例 自然金、自然銀、自然銅、自然白金などの金属の元素鉱物が延性を示します。
- 展性:叩いたり、圧力をかけたりして力を加えたときに、破壊されずに、薄く平たい箔になり元に戻らない性質です。例 自然金、自然銀、自然銅、自然白金などの金属の元素鉱物が展性を示します。
- 撓性:鉱物を折り曲げるような力を加えたとき、破壊されずに湾曲し、力を除いても元に戻らない性質です。例 石こう、滑石
まとめ
この記事では、宝石の物理的性質①【劈開 ・硬度 ・密度・ 磁性・展性・延性】について解説してきました。
地球や宝石、また自然界の仕組みは勉強しにくい分野と言われている理由は、自然界の空間的スケールが大きく、そこでおこる諸現象はさまざまな要因が絡み合っていて、単純原理や法則では説明しにくく、また地球や宇宙の歴史は、億万年前におよぶ長大な時間的スケールを持っていることが原因かもしれません。
次回は宝石の物理的性質②について解説してきます。