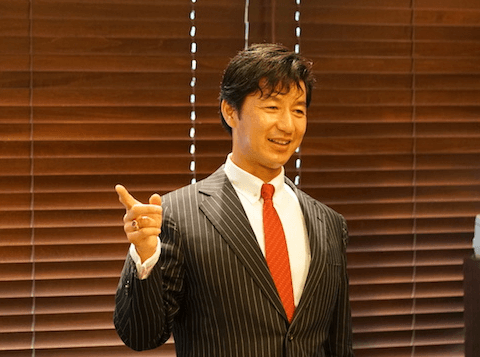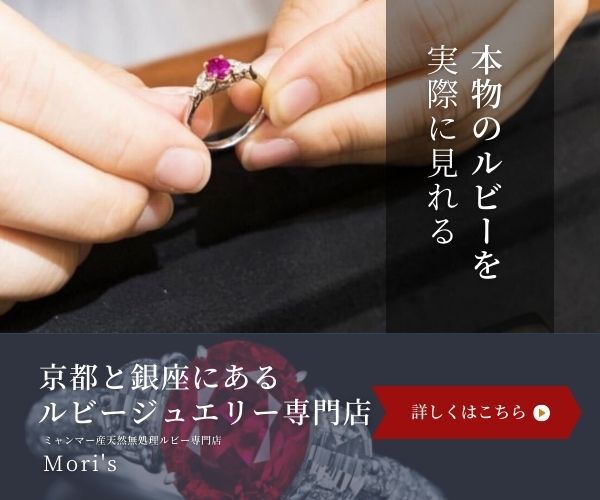ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
この他のシリーズはこちらからご覧ください
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー1【古典期から近世へ解説】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー2【中世からルネサンス】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ネオ・クラシシズム】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。
マニエリスム【内容の革新より技巧の新しさを求めた 貴族的な芸術様式】
高く評価されてしかるべき時代
マニエリスムとは、ルネサンスからバロックへの過渡期1520年頃から1600年前後までの、内容の革新ではなく既存のものの技巧的な新しさを求めた貴族的な芸術様式を言う。かつてはルネサンスのコピーなどと軽視されたが、工芸の分野では技巧的に優れたものが多く、高く評価されてしかるべきである。事実この時期、後世に誇る多くの名品を残した名工が輩出している。ジュエリーという工芸が新しいアイデアを必要とするということがこの時期の物を見ると理解できる。ジュエリーの歴史では、無視できない時代である。
職人芸から生まれた多くの名作
この時代、金細工は南ドイツでも隆盛を迎えた。その代表格がウェンツェル・ヤムニッツァーで、彼は自然の草花などをそのまま鋳造の鋳型に使い、女性像などの古典的なデザインと組み合わせた作例を残している。またミュンヘンのレジデンツ博物館に残るハンス・ライマーが作った儀式用の大きなネックレスは、大粒の宝石の回りにCの字状の渦巻き模様を配したもので、抽象的なデザインの始まりとして注目に値する。宝石のカットは、この頃から結晶の一方の頂点を切り取って平たくしたテーブル・カットを中心として、これまでの全体を丸く磨り上げたカボションカットから、ファセットカットと呼ぶ多くの切り子面を付けたものへと変化してゆく。またデザイン画というものが印刷されて市販されるようになり、デザインそのものが広く流布することで、以前ならその傾向である程度まで予測の付いた生産地が、特定できなくなるのもこの頃である。
デザイナーとして知られるハンス・コラルトが、1581年に市販したデザイン画集は見事なものだが、この時代に登場したテーブル・カットの宝石を多用したデザイン画が見られる。ファセットカットを付けた宝石は、単純なカボションよりはるかに複雑な反射光を見せて、ジュエリーの複雑さを高めていった。このように、今日残る当時の名作の多くは、マニエリスムの職人芸から生まれた。この時代の重要性がわかるであろう。
バロック【王侯たちの宮廷生活を彩った曲線と過激なまでの装飾】
聖界から俗界へ移った権力の所在
16世紀から18世紀にかけて建築や絵画、彫刻などの世界で展開された、曲線と過激なまでの装飾とを特徴とする芸術上の動きを総称する。それ以前、ルネサンス期を通じて権力を振るった法王庁はこの頃から財政的に疲弊し、代って登場するのが新興の国家権力を代表するフランスやオーストリアの王侯たちであった。
17世紀末には北方のロシアも、ピョートル大帝の下でこの動きに参加してくる。こうした宮廷での生活を彩るものとして、多くの工芸品やジュエリーが作られた。
女性のものへと変化したジュエリー
バロック期に入ってからの重大な変化は、それまで男性のものであったジュエリーが、次第に女性のものへと変化してゆくことだ。女性の服装も変わる。それまでの硬い、突っ張ったようなドレスから、柔らかい素材を使ったデコルテと呼ぶ胸刳の大きなドレスが中心となり、髪の毛もまた大きく上に結い上げられるようになる。こうした変化に伴い、新しいジュエリーが登場する。ひとつは髪飾りであり、もうひとつはジランドルと呼ぶ大きめの上部飾りから3個のペンダントを吊り下げたイヤリングである。また、胸を大きく開けウエストを絞るスタイルから、胸元からウエストにかけての大きな逆三角形の空間(露出する下着をストマッカ―と言う)が生まれ、これをカバーするものとして、セヴィ二ェと呼ばれる蝶結びなどのモティーフからダイヤモンドや真珠のペンダントを吊り下げた大柄なブローチが登場する。これはさらに大きくなり、やがて超大型のストマッカー・ブローチに変化してゆく。
ルネサンス期に頂点に達した多彩な七宝も大いに使われるが、バロック末期にかけて次第に宝石、特にダイヤモンドとルビーがまた1594年にコロンビアで鉱山が発見されてからはエメラルドが多用されるようになり、七宝の比率は減退していく。
この時代の中心となったフランスルイ14世の宮廷では、膨大な数のジュエリーが作られ使われてたが、その後の革命騒ぎのなかでほとんどが失われた。今に残るものとしては、ザクセン公国のアウグスト強健公が名工ディングリンガーを使って作らせたジュエリー類、なかでも「ムガール皇帝の宮殿にて」と題する巨大な置物は歴史に残る名品であり、この時代の金工の水準を示すものだ。
ネオ・クラシック【ポンペイ発掘がもたらした新しい動き 古典古代の美学を理想として模倣】
古代のデザイン・モティーフ復活
ルネサンスに生まれた「バロック」、「ロココ」と成長してきた過激なまでの装飾と異形のデザインは、18世紀も後半になるといささか飽きられてくる。もちろんルイ16世を中心とするフランス王家にはまだ過激装飾は強かったが、王妃マリーアントワネットがヴェルサイユの庭園の一隅に田舎家を建てたように、素朴な古典的なものへの憧れは生まれていた。祈りしも、1748年のポンペイの発掘や古代都市遺跡への旅行記などが刊行されるようになると、そうした完成度の高い古代のデザインやモティーフへの関心が高まり、古代の復活の新しい動きが生まれる。これを新古典主義あるいはネオ・クラシズムと呼ぶ。
セットもののパリュールとカメオの流行
この時代のジュエリーの一番の特徴は、パリューリュと呼ばれるセットものの流行である。これはネックレスとイヤリングが2本、それにティアラなどの頭飾りのセットで、同じ素材あるいは同じデザインで作られた。組み合わせが3点以上のものをパリュール、ネックレスとイヤリングといった簡単な2点の組み合わせをドミ・パリュールと呼ぶ。
デザインとしてはガーランドと呼ばれる華綱の連続模様を使ったものが多く、マリーアントワネットは時にこれを好んだ。その他にも、細めの木の枝や葉、繊細なリボン、中央にセットした色石などがデザインの特徴であり、そうしたモティーフを繰り返し使うことで、簡潔で重厚な印象を出すことに成功している。また女性の髪の毛は後ろに引き上げられて耳が露出するのが常であったために、大きなペンダント部分の付いたイヤリングが多く使われた。さらに古代を表すものとしてカメオが多用されたが、古代のものは少ないので、新作のカメオを生きている鶏の砂嚢に押し込んで古代色が付けられたりもした。こうした多くのジュエリーが18世紀末のフランス革命のさなか盗まれ、壊され、消滅した。代わりに赤いジャコバン党帽子に刀といった、革命のシンボルマークのようなデザインのジュエリーがこの時期に生まれている。古代ローマを理想としてそれを模倣したナポレオンの時代を経て、次のヴィクトリアンの時代に再び花開く「歴史主義」の先駆けとして、この考古学的なものへの憧れと合理的な美学を求めたネオ・クラシズムの時代は記憶に値する。
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ネオ・クラシシズム】について解説してきました。
次は近世以降からセンチメンタリズムの宝飾芸術ついて解説していきます。