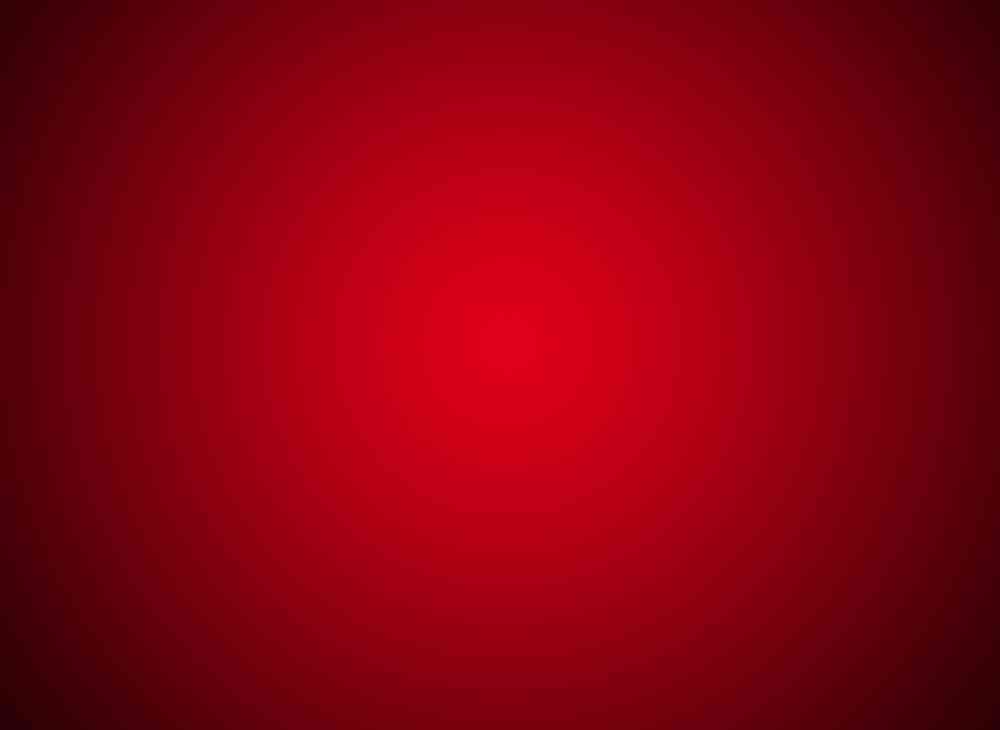「紅玉」「カルブンクルス」「カーバンクル」など、ルビーには時代と言語をまたいで、複数の別名が存在します。
これは翻訳の違いだけではありません。鉱物の識別技術がなかった時代、スピネルやガーネットがルビーと同じ名で呼ばれ、王侯貴族の宝飾品に収められていた歴史があります。
名称は、現代の宝石市場にも形を変えて続いています。同じ「ルビー」という名称でも、その品質や処理の有無は石によって大きく異なります。
この記事では、ルビーの別名がなぜ多いのか、各名称の語源と意味、そして名称の歴史が「本物を見極める眼」とどう結びつくかを、専門店の視点から解説します。
ルビーの別名がこれほど多い理由

ルビーには「紅玉」「カルブンクルス」「カーバンクル」など、時代や地域をまたいで複数の別名が存在します。
この背景には、宝石の識別技術が存在しなかった時代と、言語圏ごとに独立して呼び名が生まれた歴史という、二つの理由があります。
ここでは、ルビーの別名がこれほど多い理由について解説します。
近代以前まで宝石は「色」で分類されていた?
現代では、ルビーは「コランダム(酸化アルミニウム)のうちクロムによって赤色を呈するもの」という鉱物学的定義で明確に識別できます。
しかしこの定義が確立されたのは、近代的な鉱物学・宝石鑑別学が発展した19世紀以降のことです。
それ以前の時代では、人々が宝石を識別する基準はほぼ「色」だけだったため、赤ければルビー、青ければサファイアという分類のされ方をしていました。
その結果、スピネル・ガーネット・カーネリアンなど、ルビーとは異なる鉱物が「赤い宝石=ルビー」として一括りに扱われていました。当時は識別する手段がなかったため、「過去の人々にとって当然の認識」として受け入れられています。
複数の鉱物が同じ名で呼ばれていたことが、別名の多さの根本的な理由のひとつです。
ルビーを表す言葉は言語圏ごとに生まれた?
別名が多い理由はもう一つは、ルビーへの名称が「地域」「時代」「言語圏」ごとに独立して生まれたという事実です。大きく整理すると、主に三つの系統があります。
- ラテン語の「rubeus(赤い)」
- 古代ローマの「carbunculus(カルブンクルス)」から「Carbuncle(カーバンクル)」
- 東アジア・日本語圏の「紅玉(こうぎょく)」
まず現在の「Ruby(ルビー)」の語源となったのが、ラテン語の「rubeus(ルベウス)」です。(※詳しくは「ルビーの語源はラテン語の赤」の記事で解説しています。)
次に、古代ローマで赤い宝石全般を指した「carbunculus(カルブンクルス)」が英語圏で「Carbuncle(カーバンクル)」に形を変え広がりました。
そして東アジア・日本語圏で独自に定着した名称が「紅玉」です。
これらはそれぞれ別の文脈で生まれた名称であり、後から「同じ石を指すものとして統合された」ものもあれば、「実は別の石を指していたことが後にわかった」ものもあります。
名称が多いことの背景には、こうした独立した命名の歴史があります。
カルブンクルスとは何か?(古代ローマの名称)

「カルブンクルス」は、ルビーの別名としてよく挙げられる言葉です。
しかしこの名称は、現代のルビーと完全に一致するものではありません。言葉の意味と、それが指していた範囲を正確に知ることで、別名をめぐる混乱の構造が見えてきます。
ここでは、カルブンクルスついて解説します。
燃える石炭という語義
カルブンクルス(carbunculus)はラテン語で「小さな炭」を意味します。「炭・石炭」を意味する「carbō」に、縮小・愛称を表す接尾辞「-unculus」が付いた形で、直訳すれば「小さな炭のようなもの」です。
「燃える石炭」という表現はこの語義を意訳したもので、赤く内側から光を放つような宝石の視覚的印象が名前の由来になっています。
古代ローマの博物学者大プリニウスは、著書「博物誌」の中でカルブンクルスについて記述しており、その光輝を炎やたき火にたとえています。
これは石の化学的性質ではなく、あくまで見た目の印象「光を受けたときの赤い輝き」に基づいた命名です。語義を知ると、古代の人々がこの石に何を見ていたかが伝わってきます。
カルブンクルスが指していた範囲
重要なのは、カルブンクルスが特定の鉱物を指す言葉ではなかったという点です。
現代の鉱物学的分類でいえば、ルビー(コランダム)、スピネル、ガーネット(アルマンディン・パイロープ)、さらにはカーネリアンなど、複数の鉱物がカルブンクルスの範疇に含まれていました。
「赤く輝く石」であれば、種別を問わずこの名で呼ばれていたのです。したがって「カルブンクルスはルビーの別名」という説明は、ある意味では正しく、ある意味では不正確です。
カルブンクルスがルビーを含んでいたのは事実ですが、それ以外の石も同じ名で呼ばれていました。この曖昧さが後の時代に誤認を生む原因となっていきます。
カーバンクルと誤認の歴史

カーバンクル(Carbuncle)は、カルブンクルスの英語変形です。
中世ヨーロッパで広く使われたこの名称もまた、特定の鉱物を指す言葉ではありませんでした。そしてこの名称をめぐる混乱は、歴史に残る具体的な「誤認」の記録として今日まで伝わっています。
ここでは、カーバンクルの名称をめぐる誤認の歴史について解説します。
ブラック・プリンスのルビーが示す問題
イギリス帝国王冠の正面中央に収められた約170カラットの「ブラック・プリンスのルビー」と呼ばれる赤い石には、長い誤認の歴史があります。
14世紀後半、カスティーリャ王ペドロ1世からエドワード黒太子に贈られたとされるこの石は、その後数百年にわたって「ルビー」として扱われ、王室の宝として受け継がれてきました。
しかし、近代的な鉱物鑑別が行われた結果、この石はルビー(コランダム)ではなくスピネルであることが判明しています。
化学組成も結晶構造も、ルビーとは異なる別の鉱物です。それでも現在もこの石は歴史的名称のまま「ブラック・プリンスのルビー」と呼ばれ、帝国王冠に収まり続けています。
名称は変わらずとも、石の実体はルビーではない。これが長い誤認の歴史からくる「名前と実体の乖離」という問題の典型例です。
同じ名前でも石は違う
カーバンクルという名称もカルブンクルスと同様、ルビーを含む赤い宝石全般の総称でした。ルビーの主要産地はミャンマー・スリランカ・東南アジアなどに集中しており、ヨーロッパではルビーが採掘されません。
赤い宝石に乏しい欧州では、ルビー・スピネル・ガーネット・カーネリアンなどを識別する機会も動機も限られており、「赤い石=カーバンクル」という大まかな分類が長く続きました。
したがって「カーバンクルはルビーの別名」という説明は正確ではありません。カーバンクルはルビーを含む可能性がある名称ですが、それがルビーを指しているかどうかは別の問題です。
名称だけで石の実体を判断することには限界があります。この構造は歴史的な話にとどまらず、現代の宝石市場にも形を変えて続いています。
日本語ではルビーを紅玉と呼んでいた?

ルビーの和名は「紅玉(こうぎょく)」です。
「紅い玉」と書くこの言葉は、見た目の色をそのまま当てたように見えますが、「紅」という色彩語には単純な赤とは異なる深みがあります。
ここでは、紅玉と呼ばれるようになった文化的な背景と、なぜ紅玉が定着していったのかについて解説します。
「紅」という色が持つ文化的背景
「紅(くれない)」は、赤の中でも青みを帯びた鮮やかな赤を指す、日本独自の色彩語です。
その語源は、紅花(べにばな)の古名「くれのあい(呉の藍)」が転じたものとされており、大陸から伝来した染料植物に由来しています。
この色は、日本の歴史の中で長く希少とされてきました。紅花染めは手間と材料を要する染色であったため、濃い紅色は特定の位階にある人物にのみ許された「禁色(きんじき)」とされた時代もあります。
希少であるがゆえに格調を持ち、憧れの色として貴族社会で重用されました。単なる赤ではなく、格と希少性を内包した色彩語が「紅」です。
このように日本独自の特別な色の概念から、「紅」はルビーの和名として選ばれました。
宝石名としての「紅玉」の定着
「玉(ぎょく)」は、中国・日本を含む東アジア文化圏で古くから宝石や美しい石を指す言葉です。
「紅玉」はその構造通り「紅色の宝玉」を意味し、明治以降に西洋の宝石学が日本に導入される過程で、Rubyの訳語として定着しました。現在も国内の宝石鑑別機関において「紅玉」は正式な表記として使用されています。
ひとつ注意が必要なのは、「紅玉髄(こうぎょくずい)」との混同です。
こちらはカーネリアンを指す別の宝石の名称であり、「紅玉」とは異なる石です。見た目の色が似ていることもあり、名称だけで石を判断することの難しさを示す一例でもあります。
名称の曖昧さが生む現代の市場問題

名称と実体の乖離は、歴史の話にとどまりません。
「ルビー」という名称が持つ曖昧さは、現代の宝石市場においても形を変えて続いています。同じ「ルビー」と表記されていても、その内実は大きく異なる場合があります。
ここでは、名称の曖昧さが生む現代の市場問題について解説します。
スピネルとの混同
スピネル(MgAl₂O₄)はルビー(Al₂O₃)とは化学組成も結晶構造も異なるまったく別の鉱物です。
しかし、ミャンマー・モゴク地方をはじめとする産地では両者が同じ地層から産出されることが多く、色調も酷似したものが存在します。前述のブラック・プリンスの例が示す通り、かつてはこの二つを識別する手段がありませんでした。
現代では信頼できる鑑別機関による分析で両者を明確に区別できます。スピネルはルビーとは異なる独立した宝石として評価されており、2016年にはGIA(米国宝石学会)が8月の誕生石として正式に認定しています。
問題になるのは、鑑別を経ていない石が「ルビー」として流通する場合です。鑑別書のない石については、名称だけで判断しないことが基本です。
鑑別について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
ガラス充填処理と表示の問題
現代市場でより広く見られる問題が、ガラス充填処理(Lead Glass Filling)です。
これはルビーの亀裂に鉛ガラスを充填し、透明度や色調を改善する処理で、2000年代以降に大量流通するようになりました。処理を施されたものも鉱物としてはコランダムであるため、「ルビー」と表記されます。
名称が同じでも、無処理のルビーとは価値も耐久性もまったく異なります。
処理石は酸や高熱に弱く、日常的な使用や宝飾加工の過程で劣化するリスクがある点でも、無処理の宝石とは扱いが異なります
GIAなどの鑑別機関では「処理あり」として明記されますが、鑑別書が伴わない流通経路ではその情報が購入者に届かないことがあります。
「ルビー」という名称は、品質や処理の有無を保証するものではありません。
本物のルビーの条件

カルブンクルスからカーバンクル、紅玉まで名称の歴史を辿ってきた今、改めて現代において「本物のルビー」の条件とはどんなものなのか。
名前に惑わされないための基準を、鉱物学の定義から解説します。
鉱物学的定義(コランダムとクロム)
ルビーの定義は明確です。
コランダム(酸化アルミニウム:Al₂O₃)のうち、微量のクロム(Cr)が発色元素となって赤色を呈するもの。
これが国際的な宝石業界・鑑別機関が共通して用いる基準です。
モース硬度9を持つこの鉱物は、青いサファイアと同じコランダム種に属しますが、発色元素の違いによって明確に区別されます。サファイアは主に鉄やチタンによる発色であり、クロムによって発色する赤がルビーを定義する核心です。
この定義があるからこそ、スピネルやガーネットは「ルビーではない」と言い切れます。
かつてカルブンクルスやカーバンクルという名のもとに一括りにされていた赤い宝石たちは、現代の鉱物学の定義によってそれぞれ異なる石として識別されます。
名称の歴史が曖昧であった分、定義の明確さが現代のルビーの信頼性を支えています。
ルビーと他の赤い宝石については、以下の記事でも解説しているので、興味がある方はチェックしてみてください。
産地と非加熱(品質を左右する要素)
鉱物学的定義を満たしたうえで、さらに価値を左右するのが産地と処理の有無です。
ルビーの主要産地にはミャンマー・モゴク、モザンビーク、スリランカなどがありますが、産地ごとに品質特性が異なります。
中でもミャンマー・モゴク産は、大理石(接触変成岩)起源という地質的特性から鉄分が少なく、蛍光性が高いので、光を受けたときに内側から発光するような深みのある赤が、この産地ならではの特徴です。
処理の有無も価値に直結します。市場に流通するルビーの大半は加熱処理が施されており、これは業界で広く認められた方法です。
一方、加熱処理を施していない非加熱(アンヒーテッド)のルビーは市場全体のごく一部に限られ、同等の外観を持つ処理石と比較して価値は大きく異なります。
GIAなどの鑑別機関が発行する証明書に「No evidence of heating」と記載されることが、非加熱の根拠となります。名称だけでなく、産地証明と鑑別書を確認することが、本物を選ぶための手がかりです。
ルビーの品質について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
呼び名を知ることは本物を選ぶ出発点

カルブンクルスから紅玉まで、ルビーの名称の歴史を辿ることは、人類が赤い宝石を識別する知識をどのように積み上げてきたかを知ることでもあります。
名称が曖昧だった時代に、スピネルも、ガーネットも、ガラスさえも「ルビー」と呼ばれた歴史があったからこそ、本物を問う眼が養われました。
語源を知り、定義を理解し、処理の問題を把握することは、本物のルビーを選ぶための地図を手に入れることに似ています。
しかし、地図と実際の風景は別物です。同じ「天然無処理ミャンマー産ルビー」という言葉でも、実物を前にしたときの佇まいは石によって異なります。
深みのある赤、光を受けたときの蛍光、石が持つ静かな存在感、それは言葉では伝わりきらない部分です。
モリスでは、天然無処理のミャンマー産ルビーを中心に、産地証明・鑑別書付きの石をご案内しています。
名称や語源についてのご質問から、実物をご覧になりたいという希望まで、どうぞお気軽にご相談ください。東京銀座と京都三条の二つの店舗でお待ちしております。(来店予約はこちら)