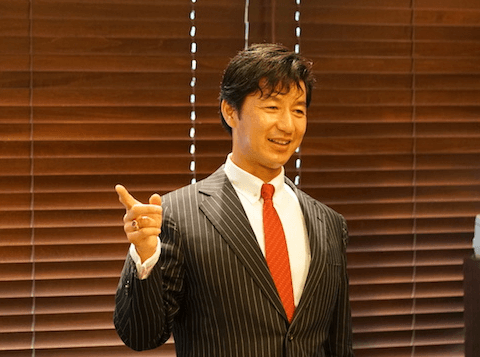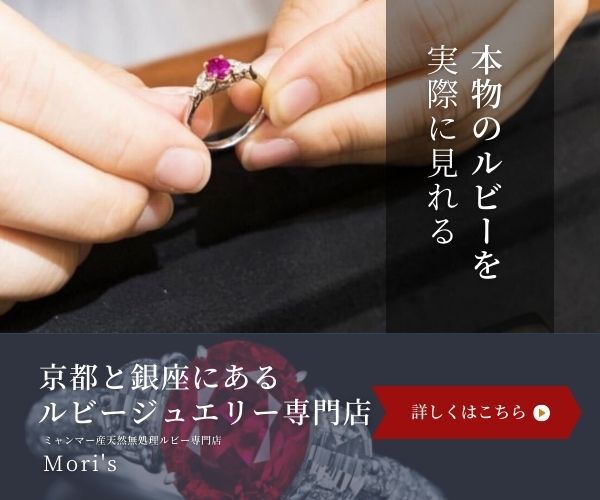ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
この他のシリーズはこちらからご覧ください
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー1【古典期から近世へ解説】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー3【ネオ・クラシシズムまで】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ベル・エポック】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。

ベル・エポック1
ジュエリー誕生を促したパリ万博アーティストと大型宝石店の登場
相次ぐ万博改正と市場の激的変化
1851年、ロンドンで開催された1回目の万博博覧会は、英国のライバルを持って任じていたフランスに大きな衝撃を与えた。同年クーデターを起こして即位した皇帝ナポレオン3世率いるフランスは、その後憑かれたように万博を開催する。1855年、67年、そして皇帝を追放して第三国共和制となった後も、78年、89年ついで1900年と、パリで万国博が開かれた。フランスの万国博の特徴は、もちろん工業面での進歩や植民地からの珍奇なものの展示もあったが、かなり大きな部分が工芸品の展示に割かれていたことだ。その工芸品のなかで、ジュエリーは銀器、実用品や置物が、この時代に重要な地位を占める。一方、買う側、つまり市場の方もまた大きく変化する。70年にナポレオン3世を追放して第三共和制をとったフランスでは、新興の産業家階級を中心として、消費構造そのものが変化する。百貨店の登場、割賊販売の施行、ショッピング・アーケードの登場など、劇的変化が生まれる。王こそいなくなったものの、しぶとく生き残った貴族たちと、こうした新興の富裕階級がパリを中心として、華やかな生活を繰り広げた時代、それをベル・エポック(美しき時代)と呼ぶ。
19世紀後期フランスデザイナー作家たち
世紀末を迎えるパリには、アトリエ風の店構えを特徴とする多くのデザイン―が登場する。デザイナーたちのほとんどが家業であり、親子まれに孫を超えて数代にわたる家も少なくない。ゴシックのリバイバルで名を売ったフロマン=ムーリス一族、重厚な中世風のデザインを得意としたジュール・ヴェイズ一族、フーケ親子、日本からの有線七宝の影響を受けたファリーズ一族、4代目が名著「19世紀フランスのジュエリー」を書いたヴェルヴェール一族、その他には、さままざな七宝を駆使したフイヤートル、角などの素材で「アール・ヌーヴォ―」風の作品をだした、リュシアン・ガイヤール、生没年のまったく不明な天才ゴートレ、それにもちろん天才ルネ・ラリックがいた。こうした個性の強いデザイナー作家たちは、時の主流であったベル・エポック様式のプラチナ・ジュエリーなど目もくれずに、アール・ヌーヴォ―ノ色彩濃い、きわめて特徴のある多くのジュエリーを世に出した。今に残る19世紀末パリで作られたこうしたジュエリーは、その個性の強さ多様さにおいてジュエリーの歴史を彩るものである。しかもその多くが、パリで開かれた万国博の工芸の展示物として作られたことを思えば、英国への反発で始まったフランスの万博熱が優れたジュエリーを生み出す原動力であったかもしれない。
ベル・エポック
パリへと殺到した王侯貴族やアメリカの大富豪そのジュエリーを一手に引き受けたグランド・メゾン
近代的な大宝石店がすべて出揃った時代
一方こうしたデザイナー・ブティック風の店舗とは別に、王制の圧力のとれた新興階級を顧客とする近代的な大宝石店も平行して登場する。グランド・メゾンと呼ばれる店がそれで、今でもヴァンドーム・サンクなどという名前で別格扱いされる場合がある。その多くは今日まで続いているものの、その後経営難に見舞われて内容が変わった店も多いが、そのほとんどはこの時代に創業するか大きくなったものだ。消費の形態も変わった。1852年には最初の百貨店ボンマルシェが開業し、1870年代にはデュファイエルの手で分割払いの制度が生まれる。今の消費が始まったのは、この時代のフランスであった。
プラチナにダイヤモンドと真珠の正統派
1800年以前に創業していたメレリオ・ディ・メレー社やショーメ社はこの頃に一段と業容を拡大し、新たにブシュロン社、それにカルティエ社が参加してくる。1906年にはヴァンクリーフ&アーぺル社が創業し、グランド・メゾンの大所は出揃うことになる。1870年代から20世紀になるまでのベル・エポックと呼ばれるこの時代に、こうしたグランド・メゾンが作り売ったジュエリーには、際立った特徴がある。それは前途のデザイナー・ブティックが新奇なデザインや作りを追求したのに比べて、正々堂々とした大振りなジュエリーが中心ということだ。プラチナにダイヤモンド、それに大粒の真珠を素材とするジュエリーがそれである。
こうしたものは、もちろんフランスの新興階級も顧客ではあったが、同時に、海外からの旅行者あるいはフランスに第二の住まいを構える外国貴族や富裕層たちにとって、パリで買うべきものの筆頭として、新しい市場を獲得していった。第一次大戦が終わるまでは、欧州には王侯貴族は嫌になるくらいたくさんいたし、彼らの多くは麗しの女性とお買い物天国であるパリへ殺到したのだ。その他にもこの頃になると、アメリカの大富豪たちやその家族がパリへやって来る。彼らの富裕ぶりはけた外れであり、大富豪たちの娘が欧州貴族の莫大な持参金と共に結婚するのもこの時代である。もちろん日本の華族たちもこうしたグランド・メゾンの顧客リストに載っている。皇室の正装用のジュエリーはこの頃にグランド・メゾンに作らせたものだ。かくして王侯貴族追放したはずのフランスが王侯貴族たちが使うジュエリーの制作をほぼ一手に引き受けるという奇妙な時代が続く。それはまたグランド・メゾンのメンバーにとっても、最も華やかで一番儲かる黄金の日々であった。そうした繁栄も第一次大戦とともに消えてゆき、グランド・メゾンと呼ばれた多くの宝石店にとっても、創業一族の追放や破産という苦難の日々を迎えることとなる。貴族を中心とする社会最後の繁栄、そしてそうした人々がファッション・リーダーであった最後の社会、それがベル・エポックであり、グランド・メゾンの時代である。
第三共和制とフランスの愚挙
美しき時代に売り払われた 国家の歴史的美の遺産
平穏な社会と新興富裕階級の美しき時代
19世紀フランスは、帝政から王政そして共和制へ、さらには大統領から皇帝となって第二次帝政を敷いたナポレオン3世が追放されてまた共和制に戻るという、まるで社会変動の問屋のような国であった。第三共和制となった1870年以降やっと社会も安定し、英国には遅れをとったものの産業革命もほぼ完成を見て、新しい資本家というブルジョア階級が定着する。王こそいなくなったもののしぶとく生き残った貴族たちと、こうした新興の富裕階級がパリを中心として華やかな生活を繰り広げた時代、それがベル・エポックである。卓越したアイデアと技術と持ったユニークなデザイナーのブティック風店舗が生まれる一方、伝統的なジュエリーもグランド・メゾンを中心に盛大に作られた時期でもある。
フランス王家伝来のジュエリー競売
1870年、フランスを追われた皇帝一族はロンドンに亡命する。もちろん、皇后ユージュニー以下の人々が使っていたジュエリーの多くも、もちだされてフランスを離れる。この頃のジョークとして、世界のダイヤモンドの産地は、南アフリカとロンドンのフランス人だというのがある。それほどに、亡命者たちは宝石をロンドンで売って、生活の足しにしたのだ。これは個人売却だが、最悪なのは、時の大統領グレヴィが、己の政治的立場を強化するだけのために下した決定、つまり、フランス王国歴代のクラウン・ジュエルをほとんどすべて売却する愚挙であった。1872年に大蔵省に回収されていたフランス王家伝来のジュエリーは、78年と84年の2回、一般公開されている。かくして、資料的価値のある若干のもの(それらはルーブルと科学博物館に渡された)を除き48ロットからなるフランス王国歴代のジュエリーは、すべて競売にかけられた。時に1887年5月12日から23日にかけてのことであった。最大の買い手は、なんとアメリカのティファニーで、彼はジュエリーをアメリカへ持ち帰ってばらばらにして作り直したものを、出所証明書と共に売却した。このように、売られたものの多くは原型をとどめず、所在のわかるものは稀であう。世界最大のコレクションのひとつが、フランス人自身の手で消えうせたのだ。こうした愚挙をする一方で、この時代のフランス人は、後年ベル・エポック様式と呼ばれる特徴のあるジュエリーを大量に作っている。しかしそれらを必要とした社会の最上層の人々がファッション・リーダーであった時代は、このベル・エポックの終焉とともに終わる。正統的なジュエリーの最終章、それが第三共和制、それも第一次大戦までの時代と言える。
アメリカからの新風 ティファニー
欧州の王室からの御用達の称号を受けた宝石商 新しい宝石を発見し、その市場化にも成功
逆転し始めたアメリアと欧州の関係
1778年にアメリカの独立が認められて以来、アメリカは欧州に対して一種の劣等感を抱き、逆に欧州はアメリカに対して、欧州に住めずに逃げ出した貧乏な下層階級の集まりと言った不思議な優越感を抱いていた。文化的にも全く未開地扱いで見下していた。しかしながら1800年頃から次第に両社の関係は逆転し始める。ジュエリーの世界でも、ティファニー社がフランス王室の宝石類を買いまくったのを始めとして、第一次大戦後は潰れた王室の宝石類の多くはアメリカの新興財閥に渡り、第二次世界大戦の終わりまで多くの重要なジュエリーが流出した。またティファニー社などは欧州の王室から御用達の称号を受け、逆に欧州の宝石商に影響を与えるようになる。
ジュエリー史に名を残すティファニー
19世紀の末に、アメリカで名を成した宝石商には、ブラック、スター&フロスト社やシュレーブなどの会社があったが、やはり群を抜いてユニークでありジュエリー史に名を残すのは、ティファニー社であろう。同社が欧州で存在感を始めて示したのは、銀器で優秀賞を獲得した1867年のパリ万国博、次いで87年に、旧フランス王室所有の宝石類の競売で最大の買い手となって欧州勢を憤激させたことだ。さらに、89年のパリ万国博では、アメリカ産の真珠や宝石類を使ったジュエリーや南アメリカ特産の蘭の花をデザインした七宝のブローチを公開して、一躍注目を集めた。創業者のチャールズ・ティファニーのプロの宝石商としての腕の冴えを見せたものと言える。彼はまた若干20歳のジョージクンツを採用し、膨大な資金を自由にさせてアメリカ国内のみならず世界中の宝石を探させた。クンツはこれに応えてミシシッピ川産の天然真珠やクンツァイト、モンタナ・サファイアなどの新しい宝石を発見し市場に送り出すことで、同社を世界の宝石業界で屈指の企業とすることに大きな力を発揮する。文化度なしと軽蔑されていたアメリカ人の会社としては異数のことだが、同社はヴィクトリア女王を始めとする多くの欧州王室の御用達となる。ティファニー社を発展させたのは、当時姿を見せ始めていたアメリカの大富豪たちであり、彼らは膨大な資金を元に、その後も欧州からのジュエリーや美術品を買い続け、その動きは第一次大戦そして第二次大戦を通じて欧州勢の無念をよそに、今日まで続いている。
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ベル・エポック】について解説してきました。
次はジャポニズムの宝飾芸術ついて解説していきます。