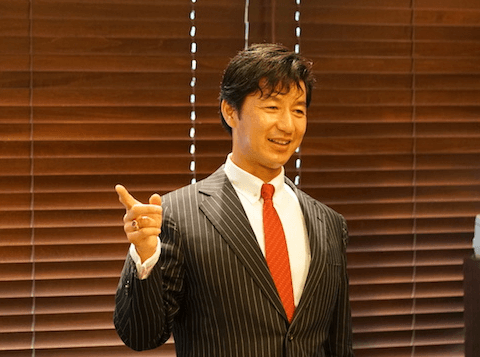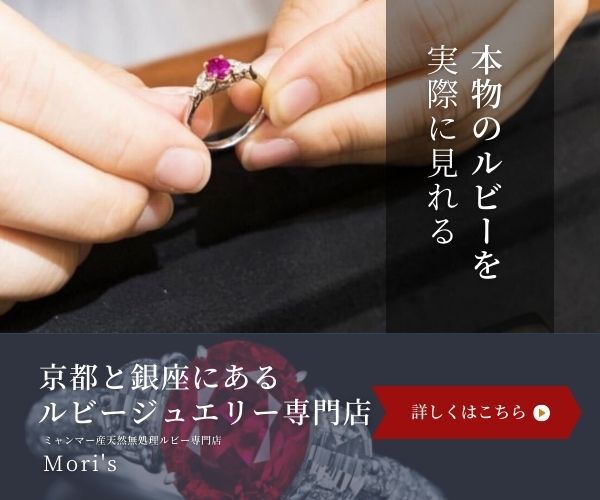ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
この他のシリーズはこちらからご覧ください
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー1【古典期から近世へ解説】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー3【ネオ・クラシシズムまで】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【エドワーディアン】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。

エドワーディアン
貴族階級の最後の輝きを放った 大振りだが繊細で軽やかなジュエリー
王侯貴族が流行を狙った最後の時代
エドワーディアンとはエドワード7世治下の英国、つまり1901年の即位から1910年の崩御までの期間を指すが、ジュエリーの暦の上ではヴィクトリア女王が公式の場に出なくなった最晩年から、第一次大戦の始まる1914年頃までがその範囲と言える。王侯貴族がファッションとトレンド・セッターであった最後の時代であり、そうした人々が使う端正で大振りなジュエリーが主流であった。
正装の貴婦人を彩った白いジュエリー
エドワーディアンの特徴を一言で言えば、「白い」ということだ。この時代に自由に使えるようになったプラチナの台座にダイヤモンドと真珠、それが素材から見たエドワーディアンのジュエリーである。その主流となったのは、王侯貴族が正式の場で着用するもので、大衆品とは言ってもそうしたジュエリーの亜流であった。したがって、この時代のジュエリーはきわめて大振りなこと、左右対称の端正なデザインであることを特徴とした。アイテムとしてはティアラやソトワールと呼ばれる腰まで届くロング・ネックレス、デコルテした胸元を覆うコルサージュ・ブローチ、首輪状で高さのあるドッグ・カラー、幅の広いブレスレットなど、いわゆる貴婦人が正装した時にのみ使えるような特殊なものが中心であった。
これらの堂々としたジュエリーの流行を促進した新しい素材がプラチナであった。金や銀に比べて少量の地金で石を支えることが可能なプラチナにより、これまでにない繊細でデリケートな感覚のジュエリーが生まれた。作りの面でも、プラチナの板を糸鋸で切り抜いて透かし細工にするピア―シングや石枠の回りなどに小さな粒状の細工を施すミルグレインなどの技術が開発され、レース状あるいは格子状といったようなデザインの可能性を広げた。このように、大型のデザインではあっても驚くほど軽量でしなやかなジュエリー、それがエドワーディアン・ジュエリーである。しかし、こうした大掛かりで手の込んだジュエリーは、第一次大戦の結果として、貴族階級が滅んでゆくにつれて、もはや必要とされなくなり、また戦後の殺伐とした社会にはそぐわないものとなり、次第に姿を消していった。これからの後の世界は、ハリウッドの芸人がファッションのトレンドを作ってゆく時代となり、それは今日まで至る。その意味では、エドワーディアンは正当な流れの最後になる。
プラチナの登場
金銀を凌ぐ強靭さの白い金属 デザインと細工に革新をもたらした特性
18世紀まで知られなかった白い貴金属
プラチナという貴金属が発見されたのは、それほど大昔のことではない。中南米に侵略したスペイン人が現地の住民がもてあそんでいた白い金属を見つけ、それを銀と間違えて本国へ送ったのが最初と言われる。少なくとも欧州で新しい金属として知られるようになるのは、18世紀のことである。プラチナの最大の特徴は、金や銀よりも硬度が高く強靭なこと、そして普通の熱では溶解できないことにある。したがって、きわめて初期のプラチナを用いた細工品の多くは、自然の塊を打ち出して作られたもので、1789年にスペイン王が法王に贈った聖餐杯も、1826年意ジョンソンが英国王のために作ったチェーンも、すべて鍛金によるものであった。プラチナがある程度自由に扱えるようになったのは、1847年の酸水素を用いたブローパイプの発明以後のことである。これによって、1755℃という高い融点を超える熱が得られるようになった。それでも宝石商がプラチナを扱うには、まだ時間が必要であった。記録では、1855年頃に、パリのフォントネがダイヤモンドのセッティングの一部に使ったと言われる。
繊細感を高めた正装用
プラチナを主素材とするジュエリーが本格的に登場するのは19世紀も押し詰まった頃で、1890年代頃から、主にダイヤモンドの爪留め用の素材として使用されるようになり、やがて全体がプラチナで作られたジュエリー群が登場してくる。折しも、英国では、エドワーディアンと呼ばれ、フランスではガーランドスタイルと呼ばれるデザインを用いた、貴族や大富豪などの正装用ジュエリーが社会のトレンドとなる時代を迎えた。基本的には「ルイ16世様式」を復活させたものだが、その主素材となったのが白いプラチナであり、ダイヤモンドと真珠であった。大量のダイヤモンドを留めるには多くの爪が必要となるが、これまでの銀と比べてプラチナはその強靭さからきわめて小さな爪でダイヤモンドを留めることができ、全体のデザインに繊細感を出すことができた。
かくして19世紀末から1925年頃にかけて、西欧のジュエリー業界はプラチナを大量に使用するようになり多くの優品が残されている。しかし、産地のロシアでの革命により、1920年頃からプラチナ地金は欠乏する。さらに、代用品としてのホワイト・ゴールドが登場し、しかもこちらの方が扱い易いために、プラチナは次第に姿を消した。不思議なことに1910年頃から西欧の宝飾技術を学び始めていた日本だけがこのプラチナの使用をやめず、今日に至るまで世界一のプラチナ使用国となっている。
アール・デコ
第一次大戦がもたらした社会現象 新しい女性たちが指示したデザイン
女性が社会進出を果たした大戦間の時代
1914年から18年まで続いた第一世界大戦は、自分たちこそ世界の中心と強烈な打撃を与えた。戦死者は1000万人を超え、それまでの支配階級であった王侯貴族が実に多くの国で姿を消した。理由はさまざま異なるものの、事態はロシアとオーストリア、ドイツ、ポルトガルへと広がり、やや遅れてトルコやバルカン諸国へと飛び火する。その間、戦争に行った男たちの隙間を女性が埋める。ここに初めて、本格的な女性の社会進出が始まるとともに、これまでの豪奢を支えてきた階級が姿を消してゆく。ジュエリーもまた、奇抜な曲線を誇示した「アール・ヌーヴォー」や大振りかつ繊細なエドワーディアンのジュエリーは、もはや、時代の女性たちには全く合わないものとなっていた。
幾何学デザインとエスニックな色彩
普通「アール・デコ」のジュエリーと言うと、きわめて男性的な幾何学的デザインのやや角張ったものを想像するが、実際には全く傾向の異なるもうひとつのジュエリーが並立の形で存在した。それは中国や日本、さらにはインドなどの装飾やモティーフを西欧風にアレンジし、インドからの色石や中国の翡翠、珊瑚などを使った、きわめてエスニック色の強いカラフルなジュエリーであった。アールデコの名称は、1925年にパリで開催された「現代の装飾美術と産業美術国際博覧会」(アール・デコラティブ)という長い名前に由来する。働く女性が身に着けられるもの、そして歴史上はじめて自分の稼いだお金で自分のジュエリーを選ぶようになった女性が好んだもの、それが幾何学形状のシャープな線を生かしたデザインであったのは十分に理解できる。丸や楕円、三角、四角、菱形といった形を地金で成形したり、その形を石でカットしたものを繋ぎ合わせたりしてデザインを構成した。
機械や工業製品を思わせる画期的なもので、デザインの優先の傾向が強く、非常に大胆かつダイナミックである。まさに時代の工業化を象徴するデザインと言えよう。エスニックなジュエリーの方はトゥッティー・フルッティと呼ばれるものが代表で、インドから渡来した彫りを入れたルビーやサファイア、エメラルドなどで鉢や籠に入った花や果物をデザインしたものだ。また、宝石に合わせて金属枠をつくるのではなく、逆に金属の台座に合わせて磨り上げたカリブレ・カットの石で模様を描いた製品なども平行して作られた。
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【エドワーディアン】について解説してきました。