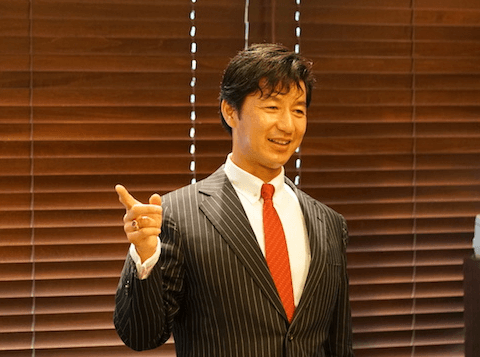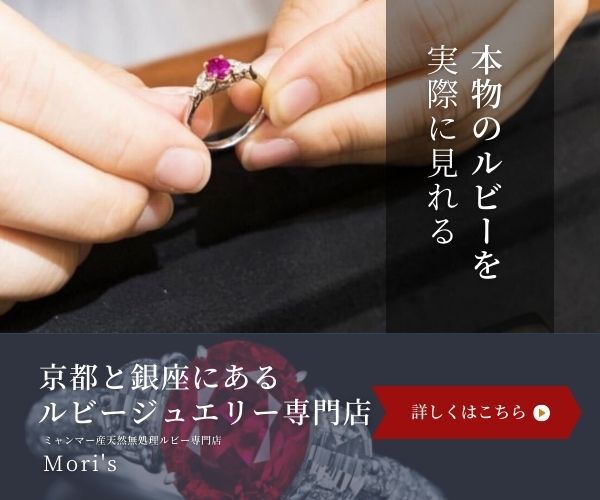ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
この他のシリーズはこちらからご覧ください
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー2【中世からルネサンスの時代】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー3【ネオ・クラシシズムまで】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【古典期から近世へヘリニズムから新古典主義】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。
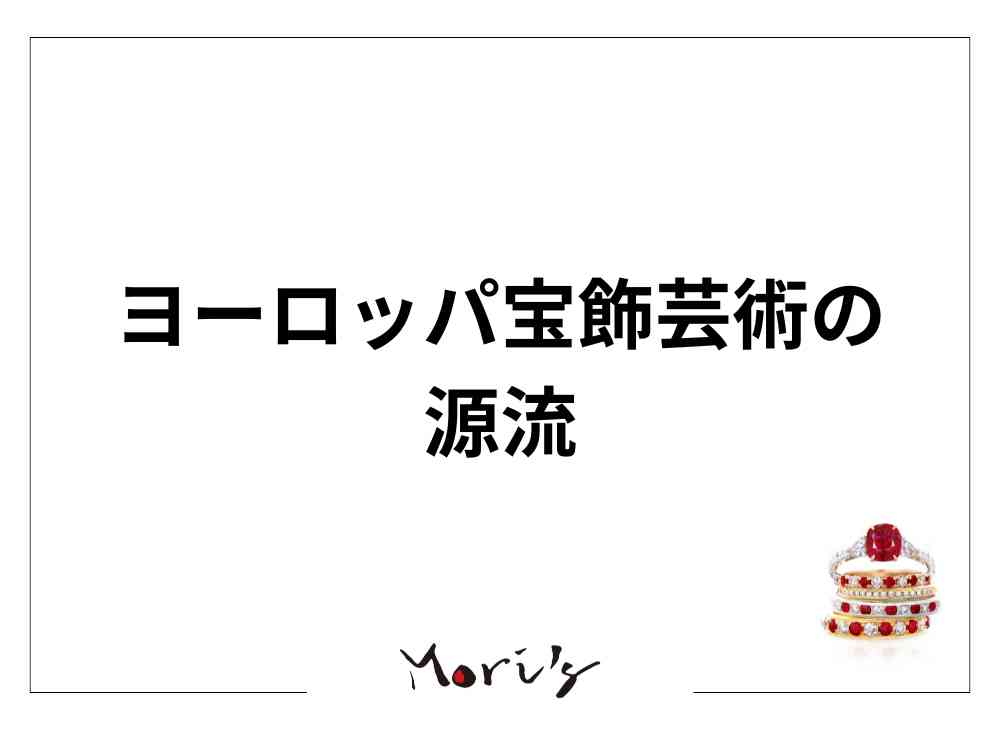
ヘレニズム時代【初の世界帝国が広めたギリシャ人の技術とデザイン】
大王の下で繁栄した金銀細工
クレタやミケーネなどで生まれたギリシャ文化は、古典期を経てアレキサンダー大王による世界帝国のヘレニズム期へと進む。大王は、ペルシャ王ダリウス3世を打ち破った時、1千トンを超える金と7千トンを超える銀とを手に入れた。大王はこうした貴金属を私せず、そのほとんどを部下にばらまき、自由に使わせた。こうしたこともあり、ギリシャにおける金銀細工は一層の繁栄をたどる。
自然モティーフの優雅で自由な表現
この間、ギリシャ人は古典期の頃のやや粗っぽい金属加工からさらに技術を発展させ、ギリシャ本土はもちろんイタリア南部やエジプト、さらには黒海沿岸に至るまでその技術を輸出している。この時代のギリシャのジュエリーの特色は、ひとつには東洋からの影響で七宝や真珠、色石などが色彩を加えたこと、もうひとつは、金で作った花模様などを金線でつなぎ合わせたような複雑な頭飾りなどが登場することだ。これは実用品であると同時に、地位のある人物の死後の用に供するものとして墓に埋葬されたようだ。
デザイン画で言えば、自然のものをモティーフにすること、そして表現の優雅さと自由さ、これがヘレニズム期の特徴であろう。2本の紐の組み合わせて作るノット(特にヘラクレスノットっと呼ぶ)もこのことのデザインで、腕輪や頭飾りに使われた。技術の面でも進歩があり、基本的には打ち出しが主ではあるが、ロストワックスによる鋳込み、さらには錫と鉛を加えた合金による融点がわずかに180~240℃程度の金蝋なども登場する。
あらゆるジュエリーに共通しているのは、作りは複雑になっているにもかかわらず、細部に見られる伸び伸びとした闊達さ、おおらかさであろう。
こうしたギリシャの工人の持つ技術やデザイン能力は、近隣の諸民族、黒海沿岸のスキタイ人や今のブルガリアにいたトラキア人などにも影響を与えたようだ。
こうした地方から出土する遺物の多くは、明らかにギリシャのデザインや技術を生かしたものであることから、スキタイの項にも書いた通り今の考古学者たちをいたく悩ませている。同じような問題は、ギリシャを属州のアーケアとしたローマについても言えることで、ローマのジュエリーの工人の手になる。このあたりがギリシャ文明のすごさであろう。
古代ローマ【ヘレニズム期のギリシャを基礎に世界帝国らしい豊富な素材】
欧州と地中海全域を領した大帝国
ローマの歴史はまず王政から始まり、やがて共和制となり、最後は帝政となる。
共和制の時代にイスパニアを領有し、ギリシャやガリア、ブリタニアなどの属州とし、カルタゴを滅ぼし、ほぼ欧州全域から地中海全域を領土としたローマは、アウグストゥス以後は帝政を敷き、史上初の一貫した統治を伴う大英帝国を完成する。以後、4世紀末に東西に分裂するまで、ひとつの大きな文化を育てる。
数多く作られた石の彫刻、カメオ
ローマのジュエリーは、そのほとんどが紀元前146年に征服して属州アーケアとしたギリシャの職人たちに作らせたものである。だから初期のローマのジュエリーは、ヘレニズム期のギリシャのものと酷似している。ローマはスペインを征服したとき、大きな金鉱山を手に入れ、同時に征服した各地にある金製品を翻刻に没収することで、金という素材を大量入手した。共和制の頃、女性の指輪なども鉄以外は認めないという質素さを見せていたローマ人も、帝政下の安逸と豪奢に次第に慣れてくる。やがて、ギリシャとは少し異なるローマ独特のジュエリーが生まれる。
最も目立つのは石の彫刻カメオだ。これは地中海地方で紀元前1700年頃から知られてい技術で、コランダムの粉末エメリーと油や血を混ぜたものを棒の先に付けて石を削った。ローマになるとダイヤモンドのチップも使われ、彫りは一段と精緻になる。すでに素材であるアゲートを加熱して色を良くする加工も行われていたようだ。このほかの、水銀鍍金も行われている。ローマらしい金細工としては、オプス・インテルラシレと呼ぶ鏨を用いた金の板の打ち抜きがある。これは鏨で切ってゆき、ついには金のレース状の模様を作り出す技術で、ローマ固有のデザインと言える。美しいブレスレットなどが遺物として残っている。また、ローマの版図が広がり東洋と常に接触があるようになったせいか、ギリシャがほとんど金のみのジュエリーであったのと比較して、真珠、色石などが数多く使われる。まあ全体としては、いかにも世界帝国ローマのものらしく、実におおらかなジュエリーが多いのが特徴といえよう。
ビザンチン【ギリシャ・ローマの古典的色彩を継承、キリスト教色の強い工芸品】
東ローマ帝王千年の神聖な文化
ビザンチン文化とは、歴史的には395年のローマ帝国分割から、1453年のコンスタンチノープル陥落までの約千年間、東ローマ帝国で培われた文化を言う。この千年の長きにわたる文化を一言でまとめることは難しいが、ギリシャの古典文化とギリシャの王教を基礎にした極めて宗教色の強い文化である。神秘性が大変に強い反面、人間的な感情の表現は乏しいとも言える。工芸の多くは平面的なデザインで、立体性のあるものは少ない。
平面的な表現と七宝と色石の多用
帝国が千年の長きにわたって存在した割には、現存するジュエリーはきわめて少ない。おそらく726~834年の偶像破壊運動と1204年の第四次十字軍による略奪のせいと思われるが、多くのジュエリーもその素材を目当てに壊されたのであろう。ビザンチンの工芸の第一の特徴は、優れた金細工にある。フィリングリーが多用され、ローマで発達したオープンワーク(オプス・インテルラシレ)さらには粒金などが見られる。金性を示すホールマークも、このコンスタンチノープルで初めて使われた。
今に残るジュエリーを見るとき、最も印象的なのは七宝の使い方である。そのほとんどはクロワゾネと呼ばれる有線七宝であり、金線による枠の中をきわめて鮮明な色の七宝で埋めることで聖人や天使、キリスト教などをカラフルに描いたジュエリーが数多くある。多くが平板な板状のものであり、それを蝶番などで組み立てて王冠やブレスレットを作っている。七宝のほかにニエロも使われている。この表現が平面的であることと、セットする色石や真珠のパターンが幾何学的となり、ひいては縦横に置かれた宝石が十字架の意味を持つようになるというところに、ビザンチン工芸のキリスト教色の強さが見える。
もうひとつの特徴は色石の多用だが、東方諸国との交易がコンスタンチノープルを経由して行われた結果であろう。色石は帝室の人々の衣服に縫い込まれたりもして使われ、七宝とあいまって、ビザンチンのジュエリーをこの上なくカラフルなものにしている。
西ローマ帝国がゲルマン民族大移動によって大きく破壊されたのに比べて、ビザンチン文化は全く新しいものは創造しなかったが、ギリシャ・ローマの古典的な色彩を保持して後世に伝えたこととなり、西欧の中世やルネサンスにまで大きな影響を与えた。
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【古典期から近世へヘリニズムから新古典主義】についてを解説してきました。
次は中世からルネッサンスの宝飾芸術ついて解説していきます。