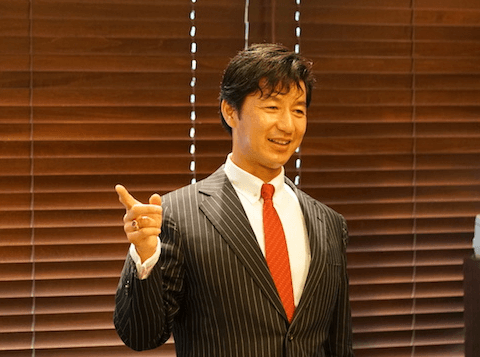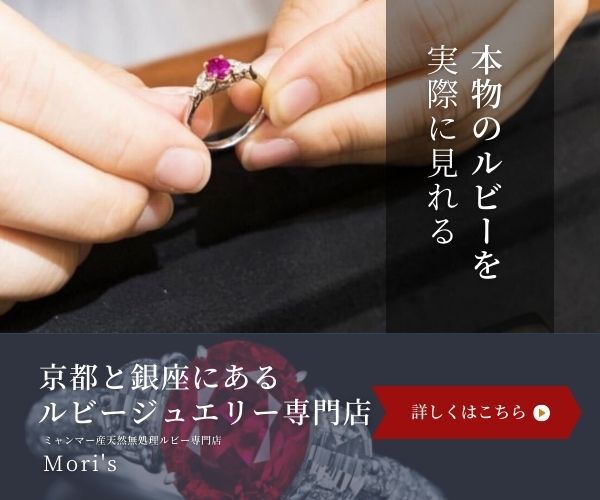ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
この他のシリーズはこちらからご覧ください
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー1【古典期から近世へ解説】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー3【ネオ・クラシシズムまで】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ヴィクトリアン】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。

ヴィクトリアン
帝国の最盛期と重なる在位期間 若い女王が先導した流行とデザイン
新しい富裕層が支えた繁栄
ヴィクトリアンすなわちヴィクトリア時代とは、正確に言えば1837年にヴィクトリアが女王として即位し、1901年に崩御するまでの64年間を指す。この世界的にも例の少ない長い統治期間中、産業革命を終えた英国は世界をまたぐ大植民地帝国を作り上げた。文字通り、英国の最盛期である。この時代の最大の特徴は、王侯貴族と僧侶に加えて産業革命で財を成した人々が新しい富裕階層として加わったことだ。64年に及ぶ彼女の時代は、便宜上、即位から70年頃までの時期と、それからの死去までの2期に分ける。
万国博で広がりを見せたデザインと素材
産業革命を通じて登場する新興階級とそれに続く市民階級のためのジュエリーが登場し、素材と技術、デザインそれぞれの面で従来と完全に異なる多様さを見せる。この意味で、近代のジュエリー産業はここに始まると言えるだろう。
1837年、うら若い女王が即位し、やがてアルバート公と結婚して9人もの子供に恵まれた時代、女性たちのファッションのリーダーは若い女王であった。ヴィクトリアン初期のジュエリーは、まだ素材の成約があったものの明るさに溢れており、大粒のガーネットや明るいロイヤル・ブルーの七宝を使ったジュエリーが生まれる。デザイン画では、女王が好んだ蛇が流行する。指輪や腕輪、ネックレス等多くのジュエリーが今に残るが、デザインの基本的なテーマはロマンティックでナチュラルなもの、つまり月や星、花、木の枝、鳥、リボン、ハートなどの手慣れたものが中心であった。文字遊びのジュエリーも、フランスから移入されて流行する。
この時代で忘れてはいけないのは、1851年にロンドンで開催された世界初の万国博の成功だ。多くの美術工芸品が展示されたことも大きいが、これを通じて世界中の工芸品が入り混じったことにより、デザインや素材の面で広がりを見せた。オーストラリアとカルフォルニアで新しい金鉱山が発見されて、素材の制約も少しずつ消えていった。
1861年、女王の夫君であるアルバート公が急死すると女王の生活が一転して暗い喪の世界へと入り、当時の建前社会にすでに存在していた、服喪の風習が女王の周りの上流階級を中心に強くなる。これを契機として、喪のためのジュエリー、モーニング・ジュエリーが大量に作られた。
その一方で、王室の喪など知ったことではないとする新しい階級の人々は、機械による量産化の始まりと新たに登場した素材で開かれた新しいジュエリー市場の客となっていく。
第二帝政期
ナポレオン3世とその妃の時代 卓越を見せたパリのジュエラーたち
豪奢を好んだ皇帝夫婦の波乱の歴史
ナポレオン1世の弟の息子、つまり甥であったナポレオン3世は、1848年に第二共和国大統領に選ばれ、次いで51年の任期切れを前にクーデターを起こして議会を解散し、同年12月に人民投票によって皇帝となる。自らナポレオン3世と名乗り、皇后ユージェ二ーと共に、いわゆる第二帝政を開く。70年プロシアとの戦争に大敗して自らも捕虜となり、蜂起したフランス国民に追われて英国に亡命、ここに第二帝政期は終わる。国民の反対を弾圧する一方、派手な植民地政策を実行し、国内では大土木事業や金融改革等を行い、自らも皇后と豪奢生活を営んだ。皇后ユージェニーは大の宝石好きで多くの宝飾品を作ったが、その多くは亡命先で売られたかその後の改革騒ぎの中で売り払われて、今日に残るものはきわめて少ない。
過去にアイデアを求めた折衷主義
要約して言えば、ナポレオン3世とその妃ユージェニーは、先代の皇帝とその2人の妃ジョセフィーヌとマリー・ルイーズ同様、特別に趣味がよかったわけでもなく、身の回りのことに格別のセンスを発揮したわけでもない。第二帝政期のジュエリーの特徴は、飛びぬけた特徴がないということにある。皇后ユージェニーはルイ16世妃マリーアントワネットに憧れた。だから、その時代の装飾モティーフの花綱や輪飾り(総称してガーランド)がこの頃から復活し、やがてベル・エポックに大流行するのはユージェ二ーの好みによるとも言える。
デザインの面でも、いわゆる「折衷主義」が時代の風潮であった。芸術家の多くは過去の遺物あるいはデザインなどにアイデアの源泉を求め、中世やルネサンスの文物、ひいてはイタリアのポンペイなどの遺跡から得られる発掘品などを広く利用した。これは、英国における「歴史主義」あるいは「考古学様式」と同じ動きと言える。こうしたジュエリーを作ったのが、パリのフロマン=ムーリス、ユジェーヌ・フォントネなどであった。彼らは、51年ロンドンの万国博に出品することで、皇帝一家だけではなく貴族たちの愛顧を受け、数多くのジュエリーを製作した。こうしたフランスの歴史主義のジュエリーは、その完成度の高さにおいて英国やイタリアのものを凌ぐと言えよう。第二帝政期が残した特徴のあるジュエリーとは、これらを指すと考えるべきであろう。
歴史主義という名の模倣
19世紀半ばの大きな潮流 異国と自国の歴史や遺物への関心
過去の技術とデザインを復元
人間、少しゆとりができれば、いろいろと歴史などを紐解いてみたくなるのは古今東西同じであろう。ヴィクトリア時代の半ば頃から、こうした歴史と過去の遺物に対しての関心が高まる。中世やゴシックへの関心もそのひとつであるし、そうしたなかイタリアでは各地の遺跡からエトルリアや古代ローマの遺物が続々と出土した。その後もスエズ運河の掘削工事やアッシリアの遺跡発見、シューリマンによる発掘など、過去への関心をかき立てるニュースが相次ぐ。このような過去の文様の技術やデザインを取り入れて作られたジュエリーを、「歴史主義」あるいは「考古学文様式」のジュエリーと呼ぶ。
アイルランドにまで及んだ歴史主義
「創造は模倣から始まる」とは、この歴史主義を語る場合、最適な言葉である。ジュエリーの市場が拡大してきた19世紀後半、ジュエリー制作に携わる人々は新しいアイデアを歴史や遺物、そして未だ見ぬ異国からの文物に求めた。そのなかでも特に歴史と遺物は、アイデアの宝庫となる。中世の残滓が残る「ゴシック」は、主に教会などの建築物の一部をデザインに取り入れて「ネオ・ゴシック」として再生した。ルネサンスの七宝を多様した絢爛たる色彩は、ジュリア―ノなどの手で「ネオ・ルネサンス」として、多くの宗教的なモティーフを伴って復活している。特に、この歴史主義の走りとなったのはカステラ―二一族で、古代のイタリア半島に居住していたエトルリア人の遺跡から発掘される金細工品を恐るべき精緻さで復元し、多くの名品を残した。フランスでもフロマン=ムーリスなどがゴシック様式のジュエリーを作っていたが、1860年代末になるとスエズ運河の完成もあいまってエジプトへの関心が再び高まり、スカラべやパピルスなどのエジプトへの関心が再び高まり、スカラベやパピルスなどエジプトのモティーフを借用したジュエリーが多く作られた。こうした動きは大国だけにとどまらず、アイルランドでは自国で発見されたタラのブローチが作られたし、スコットランドでは、現地の河川などで採れるアゲートなどの小石をカットしてケルト模様の台座にセットしたスコティッシュ・ジュエリーが作られている。
新しいアイデアを過去や異国に求める傾向は、やがて来る「アール・デコ」の時代にまでつながり、即位によって高まったインド皇帝即位によって高まったインド趣味、さらには中国と日本の文物やデザインを利用するにまで至る。まあ、すべての創作は模倣を基礎にしているのは事実だからそれでよいのだが、自分たちがの模倣する場合には「影響をうけた」と称し、アジア人が同じものを作ると「コピーだ」と騒ぐ欧米人は、身勝手なものであると思うがいかがであろう。
ヴィクトリアン2
考古学様式を生んだ歴史への関心 旅行がもたらした多様な素材
多彩に活気づくジュエリー市場
ヴィクトリアン時代も進むと、ジュエリーの素材だけでなくデザインの世界も変化を見せた。折りしもイタリア各地で遺跡の発掘が進み、エトルリアの遺物などの刺激を受けた古代風のジュエリーや英国のケルト人の遺物、あるいは自国の歴史を勉強して知った「ゴシック」のデザインなどを生かしたジュエリー群が登場する。「歴史主義」あるいは「考古学式」である。
またゆとりを持った人々が旅行をすることによって、各地の土産品のようなジュエリーが英国にもたらされる。イタリアからは貝のカメオや珊瑚、モザイクが、スコットランドからは多彩な色のアゲート類を使ったスコティシュジュエリーがボヘミアン地方から女王の喪に困り果てている上流階級と、人生を謳歌する中産階級とに二分されていたジュエリー市場は、一段と多彩に活気づいた。
ジュエリーの量産化と初のカタログ
ヴィクトリアン後期のもうひとつの特徴は、機械を利用したジュエリーの量産化が始まることだ。それまでの店主と客が相対し合って作るジュエリーから、店が勝手にデザインし勝手に作った物を店頭に並べて売る時代となった。だから、この頃初めてジュエリー製品のカタログが生まれる。初期から中期に登場したジュエリーも、この頃はまだ少しも変わらずに作られており、機械化の進展によって、かえってその数は増える。また市場そのものも、こうした安物を中心としてさらに拡大した。
ホルバイネスクと呼ぶジュエリーもこの頃に登場した。1877年にヴィクトリア女王がインド皇帝を称して即位したこともあってインド趣味のジュエリーも流行る。そうした若干の新しいことはあっても、この後期は社会にウンザリした気分の漂った時期でもあり、ジュエリーの世界でも手慣れた新しみのないものが山のように作られた時期である。こうした風潮への反発が「アーツ・アンド・クラフツ」運動を生み、「アール・ヌーヴォー」を先導したと言えよう。ともかく、このヴィクトリアン後期こそ、良くも悪くも、現在のジュエリー業界を生んだ時代でもあったことだけは確かである。
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術ヴィクトリアン】について解説してきました。
次はジュエリーデザイナーの宝飾芸術ついて解説していきます。