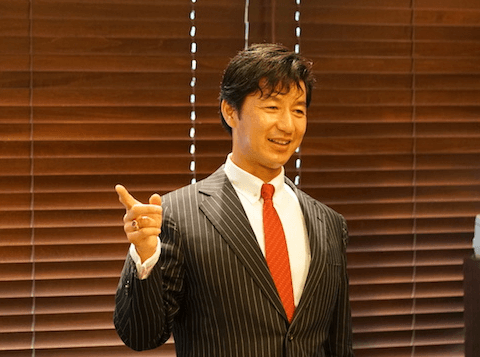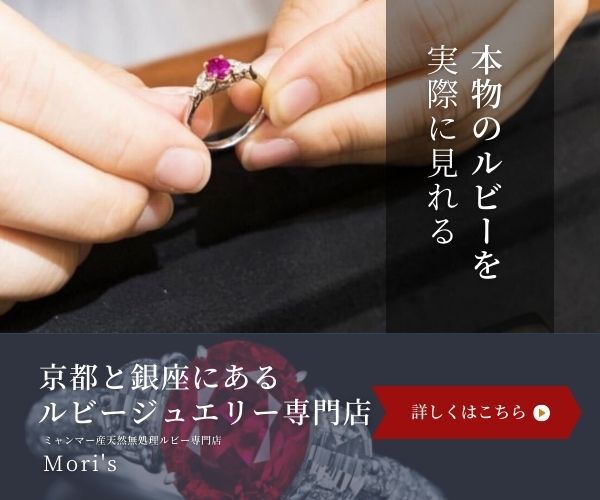ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
この他のシリーズはこちらからご覧ください
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー1【古典期から近世へ解説】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー3【ネオ・クラシシズムまで】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ジャポニズム】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。

ジャポニズム
万国博の始まりと重なった日本の開国 異文化交流が生んだ芸術上の動き
最も知られざる国の美術が与えた衝撃
日本は1639年から1854年までに、鎖国体制下にあった。この間、海外との交易はオランダと中国の2国のみと、長崎だけを通じて行われていた。開国により二本も世界事情を知るが、世界もまた、日本という国の事情や文物を知るようになる。折しも、ロンドンを皮切りに万国博が始まり、1862年のロンドン博に駐日大使オールコックがコレクションを展示した。67年のパリ博からは日本も参加し、展示された文物の多くは現地で費用調達の手段として売却され、商品として流通した。これまで全く知られていなかった日本の美術に強烈な衝撃を受け、それに影響された芸術上の動きが生まれる。これを「ジャポニズム」と呼ぶ。
ジュエリーの世界にも顕著な影響
ジャポニズムは、19世紀からの20世紀の変わり目にかけてさまざまなな分野で見られるが、金属工芸あるいはジュエリーの世界でも顕著なものであった。左右非対称を基本とする、様式化された流れるような曲線、花をはじめとする植物や昆虫と鳥、水陸の動物などのモティーフ、北斎漫画や根付などに見られる自由で創造力に富んだ人間や動物等の表現方法と、四分一や赤銅、蒔絵、漆、七宝などの素材、刀剣や刀装具などの金属工芸品などは、西欧の芸術家に深い印象を与えた。
こうした、西欧の伝統から見れば異形のものに飛びつく素地は、すでに存在していた。ヴィクトリア時代の倦怠とマンネリズム、そこに工業化が進み、いわゆる量産品が生まれる。ジュエリーの場合には、プレス加工や電鋳等を用いた製品が大量に店先に並び始める時期に当たっていた。膨大な数の内容のない繰り返しに過ぎないデザインの工芸品に、心ある人々はすでにウンザリしていた。こうした人々が新しく転換をはかるための手がかりとしたのが、異国、日本や中国、エジプト、ペルシャ、インドなどのデザインであり素材であった。なかでも、日本の文物を取り入れるジャポニズムこそ、かのアールヌーヴォーの母胎となったと言える。
また西欧ではデザインの主流ではなかったもの、つまり蛸などの海洋生物や蛇などの爬虫類、昆虫、蘭などのエキゾチックな植物、風景画などが、ジュエリーのデザインとして使われ、多くの名品を生んでいるのも、いかにも異文化の良い意味での交流を示すものとして注目に値する。
照明と宝石の関係
照明の発達ととものに変化した宝石の主流とセッティング
照明のない時代は輝きよりも色の美しさ
昔の生活には、今のわれわれには想像もつかない、あるいは全く気づかない単純なことが多々ある。そしてそれが、もろもろの事物に微妙に反映する。ジュエリーの場合、そうした日常の些事で影響を与えたのは、少なくとも1870年~80年以前には、普通の人々にとって夜の生活というものは存在しなかったということだ。つまり日が落ちれば、ほとんど寝る以外にすることはなかったのが。なぜなら、照明というものがなかったからだ。照明のない世界では、光る宝石よりも美しい色の宝石が重要となる。この点が今われわれが19世紀のジュエリー事情を考える場合、極めて大切となる。
ダイヤモンドの供給増加と電灯の普及
もちろん古代から、夜の照明として松明、蝋燭、ガス灯などは存在してきた。しかし、それはヴェルサイユに代表されるような宮殿とか王侯の館などではある程度まとまって使われていたが、それですら今の照明の水準から見れば一隅を照らす程度のものでしかない。まして、それ以下の一般家庭とか公共の部分では、夜は闇以外の何物でもなかった。こうした環境のなかで宝石として重視されたのは、光ることよりも美しい色を持つことであるのは容易に理解されよう。したがって、ヴィクトリア時代の中期以前のジュエリーを見ると、色石あるいは色のある七宝などが、少なくとも現在の様子よりははるかに大きな比重を占めているのがわかる。ヴィクトリア女王の好きだったガーネットやトルコ石、シトリン、ペリドット、グリーンガーネット、ピンク、クォーツ、ムーンストーンなどなど、今日で言う半貴石の数々を使ったジュエリーの大群がその時代には跋扈していた。しかも、この時代宝石学などはない。したがって、石の台座の底を開けることの大事さが理解されていなかったためにセットされた宝石の裏面はほとんど塞がれている。代わりにその塞いだ部分、つまり石と金属との隙間にファイルと呼ぶ箔や布あるいは紙などを入れて、色を補強したり、揃えたり、輝度を増したりする作業が行われていた。この石の留め方をクローズド・セッティングと呼ぶ。やがて照明自体も、1800年代初頭にはガス灯とアルガン式ランプが登場し、19世紀も後半になるとアーク灯や白熱ガス灯などが生まれ、1800年頃にやっと電灯が登場してくる。この夜の光の増加は、1860年代にダイヤモンド鉱山が発見され供給が増えたことと相まって光る石、つまりダイヤモンドを宝石の主流に押し上げてゆく。そして石の台座の裏面も、オープン・セッティングと呼ばれる大きく開けたものへと変化してゆく。この色石からダイヤモンドへの移行は、実は夜の照明が大きく影響していたことは、歴史の些事としてあまり知られていない。
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術【ジャポニズム】について解説してきました。
次は19世紀末の宝飾芸術ついて解説していきます。